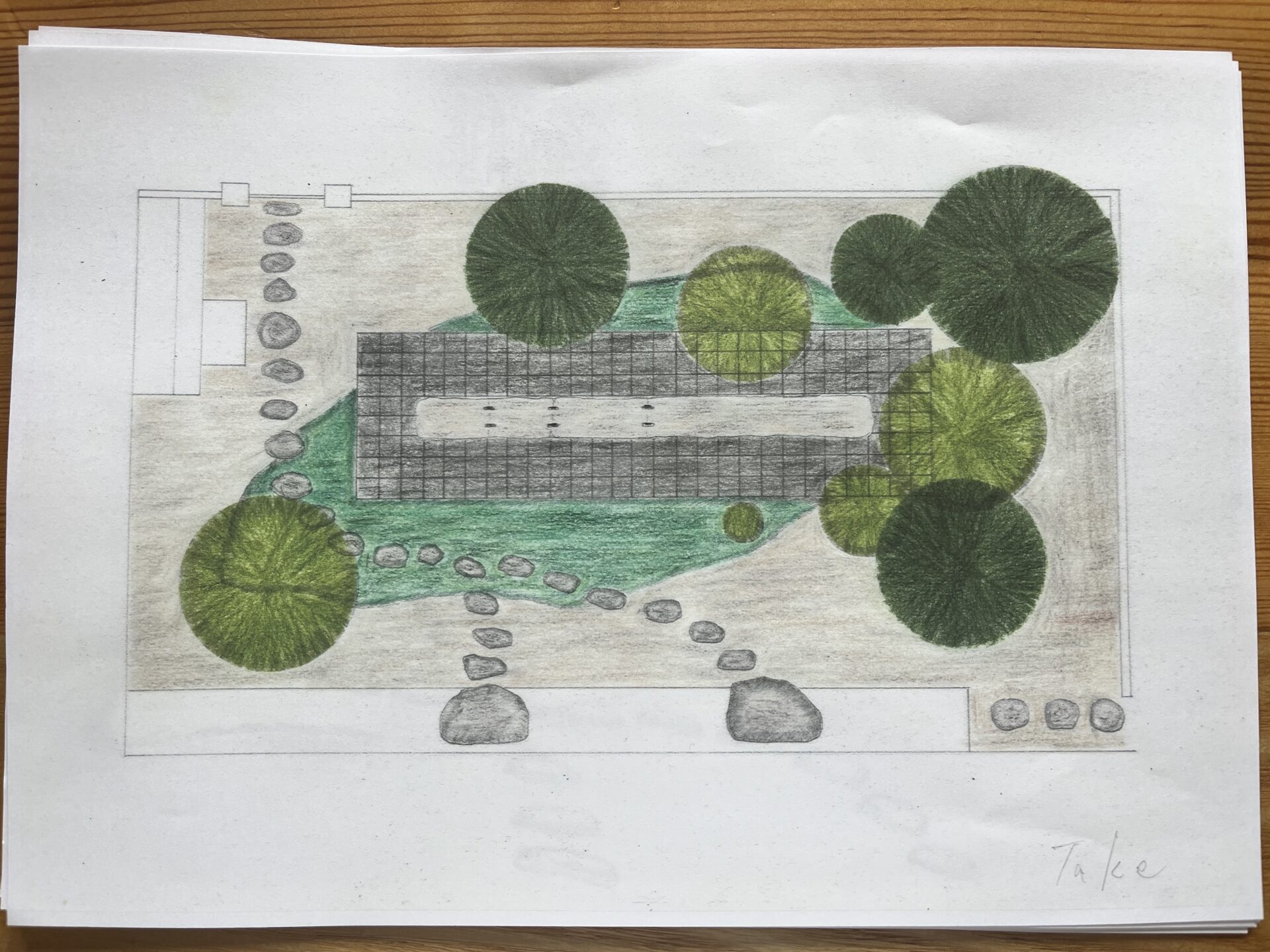X(旧Twitter)で「岡山では退治した鬼から取り上げた金棒を車止めのポールに転用している」との投稿が11万いいねを集め、色々なネット記事に掲載されています。
「鬼に金棒」ということわざの通り常に鬼とセットで考えられている金棒ですが、あまり日本の武器としては一般的ではないなあ。と思い、いつから鬼が金棒を持つようになったのかを調べてみました。
鬼、と聞いて一般的にイメージするのは角をもっている恐ろしい姿ですが、もともと日本では「隠」と書いて「姿の見えないもの・この世ならざるもの」を意味していて決まった形はなかったようです。
昔「追儺」という厄除けの宮中行事がありました(豆まきのもととなった祭祀です)。中国から渡ってきたこの行事は「4つの黄金の目と1本角」という異形の仮面をつけた「方相氏」という役職の人(190㎝程の大男が選ばれていたそうです)が先頭に立ち、それに従う侲子(しんし)や儺人(なじん)たちと共に「目には見えない悪いもの」を宮中の門より追い払う、というものだったそうです。
ところが「目には見えない悪いもの」を追っていたはずの方相氏の姿があまりにも恐ろしかったせいか、それとも「目には見えない恐ろしいもの」よりも「目に見える恐ろしいもの」の方が分かりやすかったせいか、いつの間にか方相氏(恐ろしい顔の角のある大男)がオニとして追われることになったようです。
たしかに当時の絵(Wikipediaより)をみると、先頭に立って「悪いもの」を追い払っているはずの方相氏ですが、後ろに付き従っている侲子(しんし)や儺人(なじん)に追われているようにも見えますね。
ところで「金棒」ですが、古くは「金棒」ではなく「金(鉄)撮棒」と呼ばれていました。どうやら「金撮棒」が「金棒」に省略されたようです。もともとは邪気や穢れを払う呪力を持った棒で、上記の方相氏が追儺で使用していた道具でした。方相氏がオニにされてしまったのと共に金撮棒もいつしか鬼の武器になってしまったのです。
本当は新技術を大陸からもたらしてくれた存在だったのに、「鬼」として討たれてしまった。なんていう説もある岡山の鬼―温羅-の武器としては「金棒」はお似合いなような気がします。
謂れの真偽はともかく「邪気や穢れを払う呪力を持った棒」が岡山の街角を守ってくれているのは、とっても心強いですね。

Wikipediaより