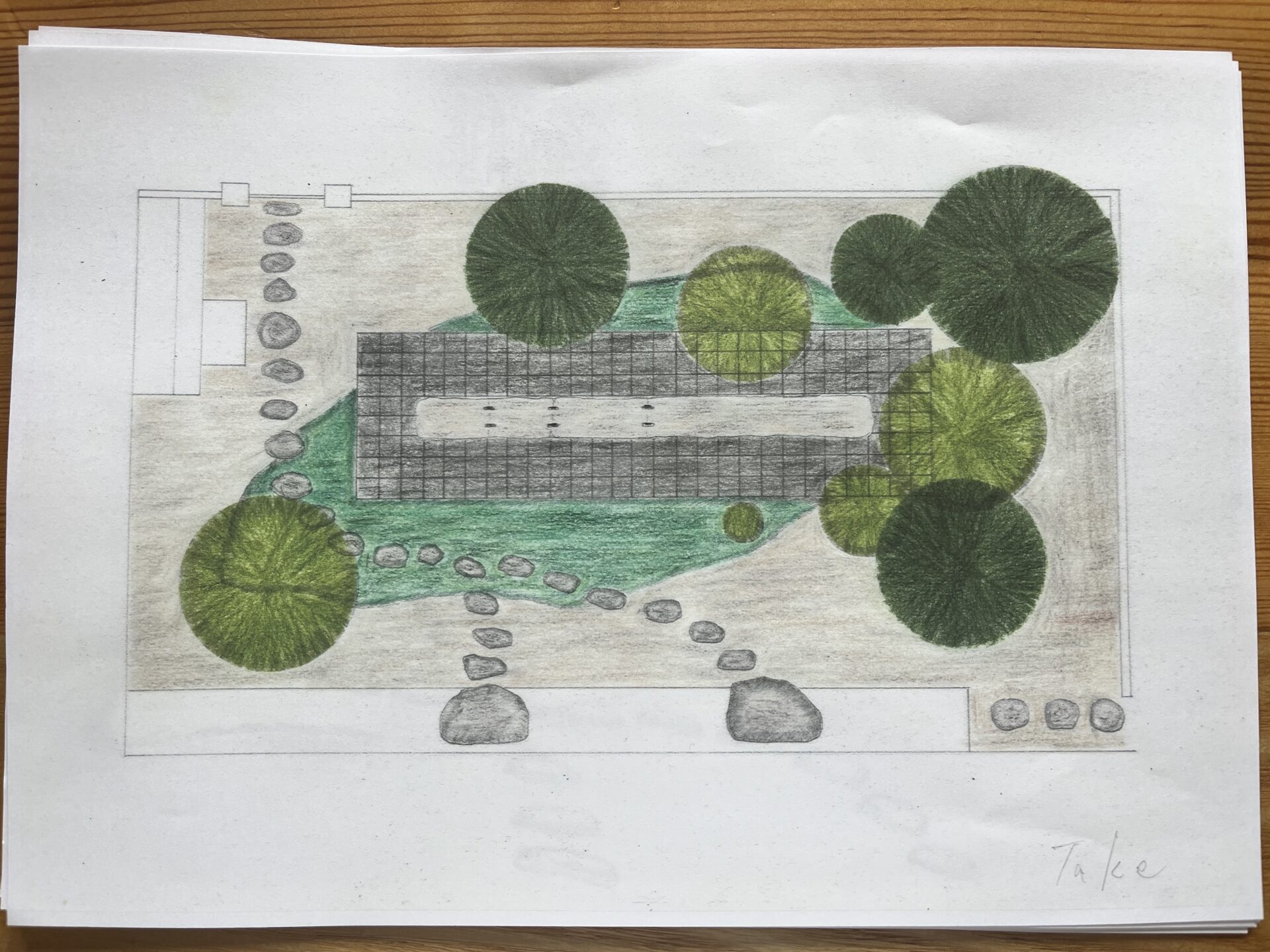「南無八幡大菩薩、我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯泉大明神、願はくは、あの扇の真ん中射させてたばせたまへ。これを射損ずるものならば、弓切り折り自害して、人に二度面を向かふべからず。いま一度本国へ迎へんとおぼしめさば、この矢はづさせたまふな。」
皆様覚えておいででしょうか?中二の教科書でご存じの平家物語「扇の的」の一節です。個人的な事情により、那須与一にまつわる「袖神稲荷大明神」にお参りにいきました。
袖神稲荷大明神は岡山県井原市西江原町の「永祥寺」境内にあるお稲荷さんで、与一が扇の的を射るときに破り捨てられた「右袖」が安置してあるそうです。「大願成就の一発の威力にあやかりたい」と信仰を集め「一発合格」稲荷として、多くの受験生が訪れています。
今回ブログを書くにあたって那須与一について調べたのですが、与一は11人兄弟で1番目の兄から9番目の兄までは平家に味方し10番目の兄と与一だけが源氏に味方したそうです。私は昔の戦は一族全てで同じ陣営に入ると思っていたので意外でした。夕食の時間とか空気悪そう。また与一が屋島の合戦で的を射る係に指名されたのは3番目だったそうです。前の二人はケガなどの理由で辞退、そのあとにお鉢がまわってきて与一も辞退したそうですが義経の圧には逆らえずに……当時の彼の年齢は15~16歳。今の高校生ぐらいの年齢で全軍のメンツ・自分の命をかけての大勝負。ものすごいプレッシャーだったでしょう。よく頑張ったね、と時代を超えてほめてあげたいです。
それにしても霊験あらたかなのが「矢」や「弓」ではなく、弓を射るのに邪魔なので切り捨てられた「袖」というのが面白いですね。目的達成のために切り捨てられたものが力を貸してくれるなんて、なんだかとってもいじらしい感じがします。屋島の合戦の扇の的を射た日付は2月18日(旧暦)。皆様の矢が目的の扇に必中しますように!